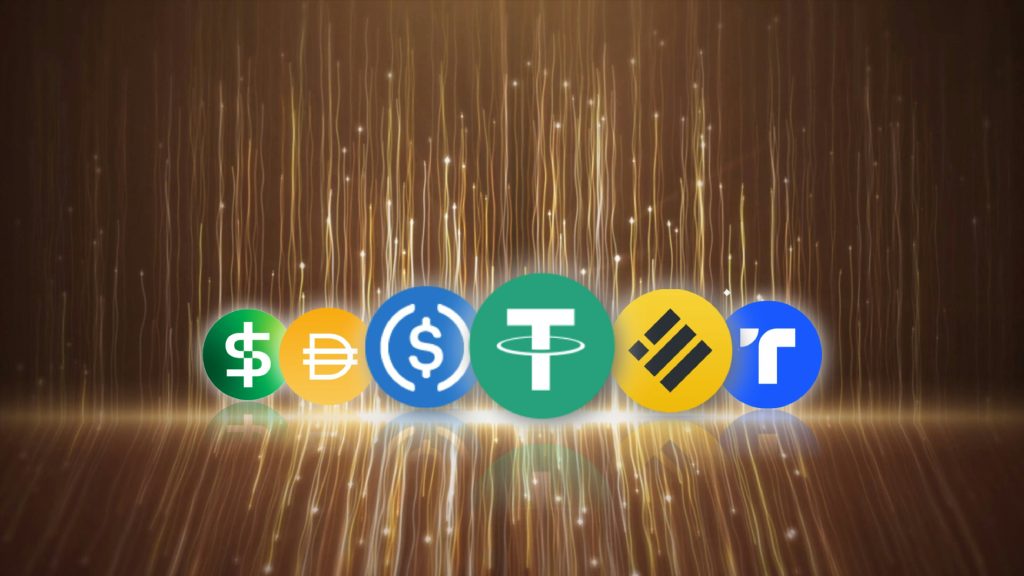
前回の記事では、ステーブルコイン「JPYC」とは何か、現金や電子マネーとの違いについて整理しました。
今回はさらに踏み込み、私たち一般ユーザーや中小企業、海外と関わる企業が具体的にどんなメリットを享受できるのか をわかりやすく紹介します。
1. 一般ユーザーにとってのメリット
私たちが日常でJPYCを利用する場合、次のような利点が考えられます。
- 送金スピードが圧倒的に速い
銀行振込は「平日のみ・15時まで」といった制約がありますが、JPYCは24時間365日、数分で相手に届きます。 - 送金手数料の安さ
銀行振込やQR決済の裏には手数料がかかっています。JPYCではブロックチェーンの利用料だけで、場合によっては数円で済むこともあります。 - 複数のサービス間で使える
電子マネーはSuicaならJR、PayPayならPayPay加盟店と、利用範囲が限られます。JPYCは異なるサービス間でも共通して利用できるため、使い勝手の幅が広がります。
たとえば「フリマアプリで売った収益をすぐに別サービスで使う」といったこともシームレスに可能になります。
2. 中小企業・製造業にとってのメリット
中小企業にとっても、JPYCのようなステーブルコインは活用の余地があります。
- 資金繰りの改善
取引先からの入金が即時反映されれば、キャッシュフローの改善につながります。特に小規模製造業にとっては「売掛金が早く回収できる」ことは大きな安心材料です。 - 小口決済の効率化
部品調達や外注費の支払いに少額を即時に送金でき、請求書処理や振込手続きの手間を減らせます。 - 透明性の確保
ブロックチェーン上の取引履歴は改ざんが困難なため、経理監査や内部統制の面でも有効に働きます。
特に「製造業は古い仕組みに依存しがち」と言われますが、こうしたツールを使うことで一歩先の効率化を実現できます。
3. 海外取引や外国人労働者にとってのメリット
JPYCが真価を発揮するのは、国境をまたぐお金のやりとりです。
- 海外取引企業
輸出入業務では、銀行を通した国際送金に数日かかり、手数料も数千円~数万円が一般的です。JPYCなら即時かつ低コストで送金可能。特に海外サプライヤーとの取引では競争力につながります。 - 外国人労働者
日本で働く外国人が自国へ仕送りをする場合、従来は送金手数料が高く、受け取りまで日数もかかりました。JPYCを活用すれば、数分で家族のスマホに届く といった体験が可能になります。
これは、外国人労働者の生活を支えるだけでなく、日本の労働市場における魅力向上にもつながり得ます。
4. デジタル給与は「本命」になり得るか?
2023年、日本でも「デジタル給与払い」が制度として解禁されました。
しかし現状は、企業が導入に慎重で、まだ一般化には至っていません。
ではJPYCが給与支払いに使われる日は来るのでしょうか?
- メリット:即時送金・低コスト・海外労働者への利便性
- 課題:法制度上の整備、安全性への理解不足、従業員の受け取り環境
つまり、仕組み自体は魅力的でも「安全かつ誰もが安心できる環境」が整うまでは、本格普及には時間がかかると考えられます。
5. 国の「デジタル円」はどうなる?
JPYCのような民間のステーブルコインと並行して、日本銀行は「中央銀行デジタル通貨(CBDC)」、いわゆる デジタル円 の研究を進めています。
- 民間ステーブルコイン(JPYC)
→ 新しいサービスや企業活動で柔軟に活用できる - デジタル円
→ 国家レベルでの信頼性を担保し、銀行や行政サービスと直結
将来的には「民間ステーブルコイン × デジタル円」が並立し、使い分けられる時代が来ると予想されます。
まとめ:JPYCは「未来のお金の予行演習」
私たち一般人にとっては「便利な送金・決済手段」として、企業にとっては「資金繰りや国際取引の効率化」として、JPYCは十分に活用価値があります。
ただし、制度や利用環境が整うまでには時間がかかるため、今は「未来のお金の予行演習」として捉えるのが現実的でしょう。
これから数年の間に、デジタル給与やデジタル円が広く普及するかどうかは、私たちがこの新しいお金をどこまで理解し、安心して使えるかにかかっています。
