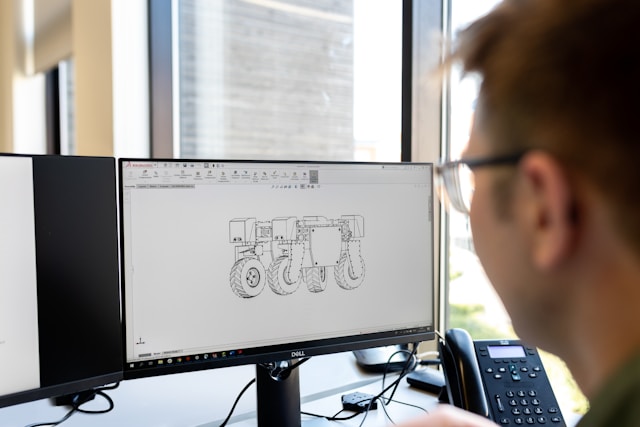
「うちはコストが安い」「短納期対応が強み」
そう自信をもって語る経営者は多いでしょう。
しかし、この2つは一見すると強みのようで
実は誰でも掲げられる“条件反射的な売り文句”でもあります。
真の差別化とは、“安さ”や“速さ”の先にある「提案力」
つまり、VA・VEの実践力にこそ存在します。
下請け構造に潜む“思考停止”の罠
中小製造業の多くは大手企業のサプライヤーとして、発注仕様に沿ってモノを作る立場にあります。
そのため、「言われた通りに作る」ことが日常化しやすく、
知らず知らずのうちに“受け身体質”になってしまうケースが少なくありません。
しかし、現代の製造現場では「安く」「早く」作るだけの存在価値は急速に薄れています。
資材高騰、人件費上昇、AI・自動化の普及…。
この環境下では、「低コスト・短納期」はもはや当たり前の前提条件であり、
強みではなく“最低条件”になりつつあるのです。
企業価値を高める“提案型VA・VE活動”とは
では、どうすれば中小企業が発注側(親会社)にとって“なくてはならない存在”になれるのか。
答えは、「VA・VEによる提案型技術力の発揮」にあります。
🔹 VA(Value Analysis)による付加価値提案
既存製品・既存工程に対して、
• 加工工程を減らす工夫
• 代替素材の提案
• 治工具・段取りの改善によるコスト低減
など、“同じモノをより効率よく、価値高く作る”提案を行う。
この積み重ねが
「あの会社は現場をよく知っている」
「コスト構造を理解している」
という信頼につながります。
🔹 VE(Value Engineering)による設計段階での関与
さらに上流工程、設計・試作段階から関与できる企業は強い。
「この設計では加工が複雑になりますが、こう変えるとコストが◯%下がります」
「量産を見据えたら、この形状の方が治具レスで対応できます」
こうした“設計協働”のVE提案こそ、サプライヤーとしての存在価値を決定づける武器です。
中小企業の“現場対応力”こそ最大の武器
中小企業の最大の強みは、柔軟な対応力と判断スピードにあります。
大手企業が部門横断的な調整に時間を要する一方で、
中小企業では“現場の判断”で即日対応できるケースも多い。
ここにVA・VEの考え方を掛け合わせると、
「小回りが利く=課題発見から提案までが速い」という、
まさに“スピード価値”が生まれます。
実際、優れた中小製造業は、
• 試作段階からの仕様改善提案
• 製造現場目線の効率化アイデア
• 品質・工程両立のための治工具開発
といった“提案セット”を武器に差別化しています。
この“提案型ものづくり”こそ、今後の中小企業が生き残る道です。
「つくる」から「考える」企業へ
VA・VEを実践できる企業は、単なる「モノづくり」企業ではありません。
「考えるモノづくり」企業です。
発注元に対して「受け取る側」ではなく「提案する側」に立つ。
これは技術力だけでなく、社内文化や社員意識の変革でもあります。
現場の一人ひとりが「どうすればもっと良くなるか?」を考える。
この姿勢こそが、VA・VEの真髄であり、企業の競争力の源泉なのです。
VA・VEがもたらす“信頼の連鎖”
VA・VE提案を通じて得られる効果は、コスト削減だけではありません。
• 技術的信頼が積み重なり、試作・開発段階から声がかかるようになる
• 結果として単価交渉の主導権を握りやすくなる
• 他社との差別化によって長期取引の安定化が図れる
つまり、VA・VEは「単価を下げる活動」ではなく、
企業価値を高める“戦略的活動”なのです。
まとめ
「VA・VEをやる」ではなく、「VA・VEで生き残る」。
コスト削減を超えた“提案力”こそが、
中小製造業にとっての最大の競争力である。
最終章では、「VA・VEは分かっていても、なぜ現場で根付かないのか?」
という課題に切り込みます。
VA・VEは知識や手法だけではなく、“人”と“組織文化”の問題でもあります。
社内教育、ベテランの登用、外部人材との連携
これらを駆使して“提案できる技術文化”をどう育てるか、
中小企業の未来を見据えて解説します。

