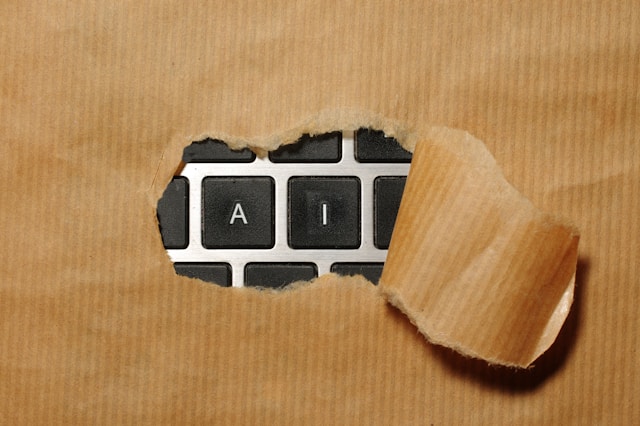
AIに正しい答えを聞く前に、私たちは正しい“問い”を持てているだろうか。
AIが身近な存在になりつつある今、そんな問いを自分に向ける機会が増えました。
ツールとしてはすでに十分に使える。文章も書けるし、資料も作れる。
けれど、使えば使うほど感じるのです。
AIの本当の価値は「問い方」にこそ宿る ということを。
■ 「正しい答え」から「意味ある問い」へ
私たちは長い間、「正解」を求める社会の中で生きてきました。
学校教育では模範解答を目指し、会社では「成果」と「効率」を重視する。
つまり、“正しい答えを導ける人”が優秀とされてきた時代です。
しかしAI時代においては「答えを出す」ことはAIが最も得意な領域 です。
むしろ人間が競うべきは、その“前段”
つまり、「何を問うか」 という部分なのです。
たとえば、AIに「いいプレゼン資料を作って」と頼むと、整ったスライドが返ってきます。
でも、そこに「誰の心を動かしたいのか」「何を伝えたいのか」が欠けていれば、
それはただの「整った情報」でしかありません。
AI時代に問われているのは、
「どんな問いを立てるか」=思考のリテラシー そのものです。
■ AIが映し出す「思考の浅さ」
AIと対話していて感じることがあります。
それは、AIは私たちの“問いの浅さ”を正直に映し出す鏡 だということ。
たとえば、AIに「今後のビジネスで成功するには?」と聞くと、
どこかで見たような一般論が返ってくる。
しかし、「なぜ人は“成功”を目指すのか?」と聞くと、
まったく違う深みのある対話が始まる。
つまり、AIが“つまらない答え”を返すのは、
AIが悪いのではなく、問いが浅いから なんです。
これは痛烈です。
これまでの「正解主義」に慣れた思考が、AIとの対話でまるで裸にされるような感覚。
でも、そこにこそ新しい学びがある。
■ 「問い」は未来を開く鍵
“問い”は、未来を方向づけるコンパスです。
「正しい答え」を求める思考は、過去の延長線上にあります。
一方で、「新しい問い」を立てる思考は、未来を切り拓く。
AIの世界は、いわば 「問いを育てる時代」 に入ったとも言えます。
たとえば、
- 「AIができること」ではなく「AIと一緒に何をしたいか」
- 「人間に残る仕事」ではなく「人間にしかできない価値とは何か」
こうした“再定義の問い”を持てるかどうかで、
これからの個人や組織の成長スピードが変わっていくはずです。
■ 思考リテラシーとは「問いの設計力」
ここで少し整理してみましょう。
AI時代に求められる“思考リテラシー”とは、
単なる情報の読み書き能力ではなく、次の3つの力に集約されると思います。
1. 観察する力
― 表面的な情報ではなく、背景・構造・関係性を読み解く視点。
2. 構造化する力
― 問題を分解し、どの部分をAIに任せ、どの部分を人が担うかを整理する力。
3. 問いを立てる力
― 「なぜ」「どうすれば」「そもそも」を繰り返し、思考の深度を上げていく力。
この3つが揃うことで、AIは単なる“便利な道具”から、
“知の共同制作者”へと変わっていくのだと思います。
■ 「正解よりも対話を」へ
これまでの社会では、会議でもプロジェクトでも「結論」が求められました。
けれどAI時代においては、
「結論を急がず、対話を重ねること」こそが価値 になる気がします。
AIは、私たちに即答をくれる。
でも、本当に大切なのはその“過程”で、自分の思考を見つめ直すこと。
つまり、AIとの対話とは、自分自身との対話 でもあるのです。
■ まとめ:AI時代の「問い」は、私たちの鏡
AIは私たちに「何を知りたいのか」を問う存在です。
だからこそ、AIとどう向き合うかは、
私たちが自分自身をどれだけ深く見つめられるかにかかっている。
“問いを創る力”とは、
自分の中にある価値観や世界の見方を再発見する力でもあります。
そしてその力こそ、AI時代の「人間らしさ」なのかもしれません。
■ 次回予告
第3回では、さらに一歩進んで
「AIツール乱立時代 何を選び、どう使うべきか」 に焦点を当てます。
未来の知的共創について、一緒に考えてみたいと思います。

