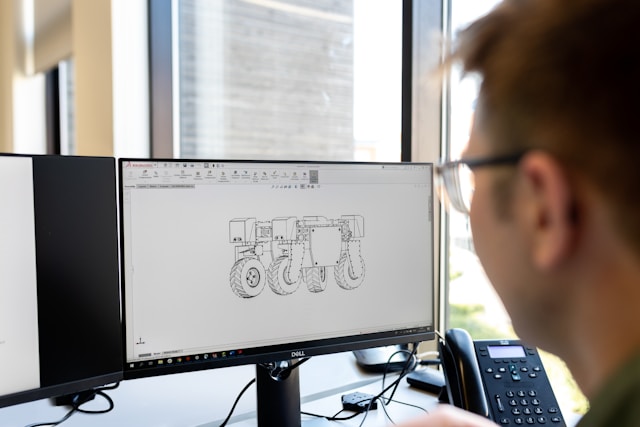
「うちの会社でもVA・VEをやろう!」
そう意気込んで始めても、しばらくすると形骸化してしまう…。
多くの中小製造業が抱える共通の悩みです。
なぜVA・VEは“やる”ことが難しいのか?
それは、VA・VEが単なる技術手法ではなく、“考え方と文化”だからです。
今回の最終章では、VA・VEを企業に根付かせるための
「人づくり」「仕組みづくり」「環境づくり」を考えます。
VA・VEの本質は「問題意識」と「課題解決力」
VA・VEを実践する上で最も大切な要素は、「問題を発見できる人材」です。
“言われたことをこなす”ではなく、“なぜこの作業をしているのか?”を考える。
つまり、「課題を発見し、改善策を構想できる力」が問われます。
この力を育てるには、日々の現場の中で
• 「なぜこの工程が必要なのか?」
• 「目的に対して最適な手段か?」
• 「もっと良くできる方法はないか?」
と問い続ける習慣が欠かせません。
VA・VEとは、“常に問いを立てる文化”を育てることでもあるのです。
誰でもできるわけではない “経験×応用技術力”の重要性
VA・VEは、単なるコスト削減提案ではありません。
技術的裏付け、経験に基づく判断、製品や工程への深い理解が不可欠です。
つまり、「誰でもすぐできる技術」ではなく、
“経験と応用力を持つ技術者”の存在が鍵になります。
例えば、
• ベテラン職人の持つノウハウ(“手の感覚”や“現場勘”)
• 試作・治具製作で培った加工の最適化知識
• 設計段階での実現可能性を見抜く力
これらはマニュアルでは伝わらない、暗黙知=企業の資産です。
その暗黙知をVA・VE活動の中に取り込み、“知を共有する仕組み”をつくることが
企業の強さに直結します。
教育・仕組みで育てる「VA・VE文化」
VA・VEを根付かせるには、単発の研修やスローガンでは不十分です。
「現場で考える力」を継続的に引き出す仕組み化が必要です。
🔹 社内教育制度の整備
• 若手社員に対しては「VA・VE思考」基礎教育を実施
• 現場での改善事例を共有する“見える化ボード”を設置
• 成功事例を表彰・評価に反映し、モチベーションを高める
🔹 ベテランの登用と知識伝承
・ベテラン社員を「技術伝承リーダー」として位置づけ、
・若手が一緒にVA・VE案件を進めるOJT形式で育成する。
・ベテランの経験値を“形式知化”する取り組みこそ、
世代交代期の中小企業における重要なテーマです。
🔹 外部人材・外部連携の活用
VA・VEの思考は、外部視点が加わると一気に深化します。
• 他業種出身エンジニアの採用
• 技術コンサルや設計支援会社との連携
• 取引先や大学との共同開発
“内輪の改善”に留まらず、“外の知恵を吸収する文化”がある企業ほど
VA・VEが機能しやすいのです。
経営者が担うべき“仕掛け役”としての責務
VA・VEを文化として定着させるためには、経営者・管理者層の理解と支援が不可欠です。
• 「VA・VEをやれ」ではなく、「VA・VEを評価する」
• 「コストを下げろ」ではなく、「価値を上げろ」
• 「やる人」を選ぶのではなく、「全員が考える環境をつくる」
このマインドチェンジが、組織を変えます。
VA・VEを単なる“改善活動”ではなく、経営戦略そのものとして扱う姿勢が問われます。
“VA・VE人材”が会社の未来を変える
最終的に、企業の競争力は「人」で決まります。
図面を読むだけではなく、「図面の裏側(設計思想)」を理解し、
さらに「現場で最適解を導き出す」人材。
そんな“VA・VE人材”が社内に一人、二人と育っていくことで、
企業は確実に変わっていきます。
やがて、
「あの会社は提案してくれる」
「ただ作るだけじゃない」
という評価が定着し、長期的な信頼と新しい仕事の機会を生み出していくのです。
まとめ “VA・VE文化”を次世代へ
VA・VEとは、単なる手法ではなく「考える文化」である。
それを支えるのは、“人”であり、“組織”である。
教育・登用・仕組み化・連携
これらを通じて中小製造業が“提案できる技術集団”へ進化していくこと。
それこそが、これからの時代を生き抜くための最も確実な投資であり、
未来への“技術文化の継承”なのです。
シリーズ総括:「VA・VEで未来を創る」
第1回:VA・VEの基礎知識編
👉「価値を生むとは何か」を理解し、VA・VEの考え方を学ぶ
第2回:中小製造業の命綱としてのVA・VE
👉「提案力」で企業価値を高める戦略的活動を理解
第3回:VA・VE文化の定着と人づくり
👉「継続」と「人材育成」で組織に根付かせる
