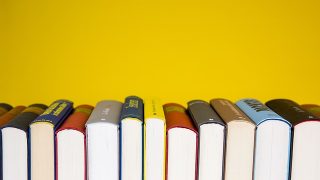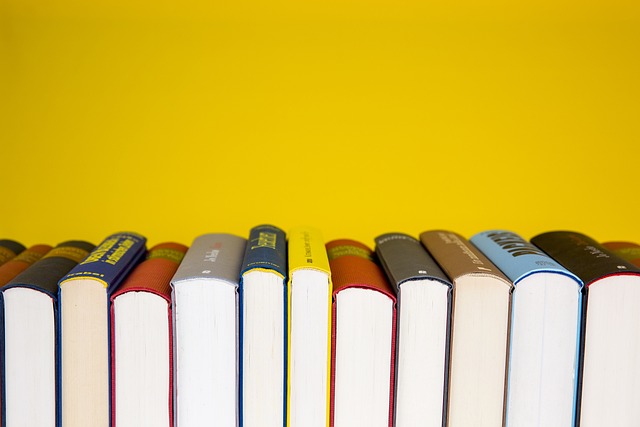
お国の方向性としても「デジタル人材育成」や「デジタルリスキリング」
に力を入れております。
そんなお手伝いを企業向けに行っておりますが
世代によって伝えるべき(学んでいただきたい)内容は変わって来ます。
・中堅から管理職へ(35歳から45歳位)
実はこの世代が少し難しい世代になります。担当が20代にどんなお仕事の進め方をしてきたかで
大きく道が別れます。
しかし大切なのは、会社の立場的にキーマンになり得ると言うことです。
若手と管理職や経営層に挟まれて、大切な調整役としての役目があります。
多少上司から厳しく言われ無茶振りされても、若手へは優しくお仕事を任せたり
誰に聞けば、誰に助けてもらえば最短距離でことが進められるか?
社内の人間関係(社内政治)を理解して振る舞えるのが中堅所になります。
デジタル知識に関しては経験含めて若者世代(デジタル世代)とは差もあるでしょう。
中堅所が頑張るべき所は、お仕事のマネジメント(裁き処理)
しかし勝負するのはそこでは無いです。
固有の深掘りした技術論は若者世代や専門家に任せましょう。
中堅所が頑張るべき所は、お仕事のマネジメント(裁き処理)になります。
業務の段取りを理解して、自分以外の若手メンバーや他部者の課題にも目を配り
最適解を導いて行く、準管理職の役割です。
漠然とした解説では難しいでしょうから、具体的にはアルゴリズムが組める人材です。
アルゴリズムとは、解が定まっている「計算可能」問題に対して、その解を正しく求める手続きをさす。
算法、計算手順、処理手順とも和訳される。
言うなれば、手順書や業務マニュアルが作れる人材教育になります。
人が感覚や、うる覚えで行っているアナログ業務を、順番に処理手順化して、デジタル的(タスク分解)
出来る能力です。これは言うは易しですが、多くの方が苦手意識もあり
そもそもの文書書くのも苦手、箇条書きに書くのも苦手
マニュアルなんて人生の中で逃げて来た…
こんな意識もあり、出来れば避けたい上位の業務に当たります。
しかしデジタル化の最初としては、仕様(仕組み)手順化は必須業務になります。
これはやはり性格にもよりますが、経験や教育の中からしか身に付きにくい内容になります。
システム開発段階でのユーザーヒアリング情報からの仕様落とし込み業務(プログラマーへの橋渡し)になります。
ここが出来れば後は若手に任せてノーコード実装などを進めてもらいます。
もう一つのヒント(近道) 対話型AIの活用
この仕様(アルゴリズム化)には対話型AIもお得意な分野です。
逆に言うと使わない手は無いです。
「このデータを使い、このような結果を導くための仕組み作りのアルゴリズム(フロー手順)を教えて」
こんな感じで指示をすると、あら不思議…AIが即座に応えてくれます。
これを使いこなすのも中堅所のデジタルスキルになります。
文書だけでの説明は非常にややこしくなり伝わり難いかもです
後で時間を作って体系図を整理してみます(いつになるかは未定)
みなさんのお役に立てれば幸いです。