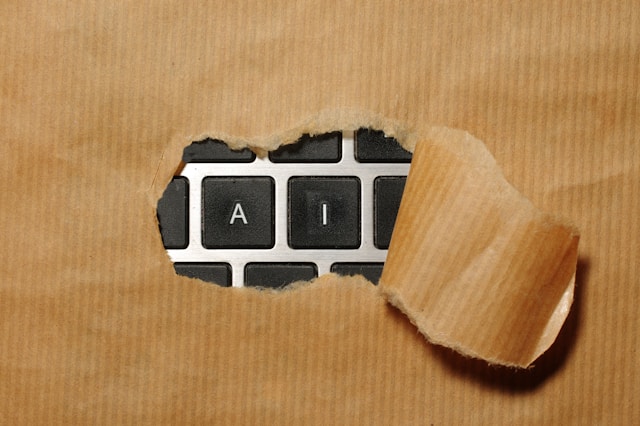
■ 黒船がやってきた、あの日のように
もし今のAIブームを、たとえで表すなら
それはまさに「黒船来航」かもしれません。
ペリーが浦賀に姿を現した1853年、日本人はその光景に度肝を抜かれました。
「何だこれは?」「自分たちの知る世界とまるで違う…」
そんな驚きと戸惑いの中で、時代は一気に動き始めます。
AIも同じです。
ChatGPTが登場したとき、多くの人が驚きと興奮を覚えました。
「人間みたいに話す」「仕事を代わってくれる」「文章が上手い!」
しかしその一方で、
「これって、どこまで信じていいの?」「自分の仕事はどうなるの?」という不安も広がりました。
つまり、私たちはいま再び“黒船を見上げている”のです。
■ 「理解できないスピード」への戸惑い
AIが怖いのは、もしかしたら“速すぎる”からかもしれません。
IT革命の時代、私たちはゆっくりと「デジタル」に慣れていきました。
パソコン、メール、インターネット、スマホ…。
便利さに驚きながらも「使い方を覚えれば」追いつけた時代です。
でもAIは違います。
昨日使えなかった機能が、今日には当たり前のようにアップデートされている。
理解する前に、次の波が押し寄せてくる。
そんな理解の前に進化するテクノロジーに、私たちの思考が追いつかない。
そのスピードのギャップこそが、今のAIへの戸惑いの正体ではないでしょうか。
■ 「AIを理解したい」という人間の習性
私たちはどうしても、AIを「理解しよう」としてしまいます。
どんな仕組みなのか?
どう動くのか?
どこまで正確なのか?
でも、本当はその姿勢こそが、AIを難しくしているのかもしれません。
AIを完全に理解することは、たぶん誰にもできません。
なぜなら、AIの学習や思考は人間の脳のように複雑で、しかもその構造自体が常に変化しているからです。
つまりAIは、「理解する対象」ではなく「共に考える存在」なのです。
少し肩の力を抜いて、
「全部はわからないけれど、まずは一緒に使ってみよう」
そんな距離感が、AI時代のスタートラインになるのかもしれません。
■ 「正解を求める思考」とAIのすれ違い
特に仕事の現場では「AIにどう使わせるか」よりも「AIが何を答えてくれるか」が気になります。
でも、ここに大きなすれ違いがあります。
これまでの社会は「正解を出すこと」が評価される世界でした。
試験も仕事も、目標もゴールも、常に「答え」がありました。
一方でAIは「答えのない世界」を平気で広げていきます。
「こんな見方もありますよ」
「別の視点ではこうも考えられます」
まるで鏡を何枚も見せるように、可能性を増やしていく。
ここに戸惑うのは当然です。
でも同時に、この「答えのない広がり」こそが、AIの魅力でもあります。
つまりAIは、私たちにこう問いかけているのです。
「あなたは、本当は何を実現したいのですか?」
■ “未知”への抵抗は“希望”の裏返し
黒船を見た江戸の人々も、最初は恐れたと思います。
「何かを奪われるかもしれない」と。
けれど、その後の日本は開国を選び、
産業も、教育も、価値観も大きく変わっていきました。
AIもまた、同じように「未知」としてやってきた存在です。
恐れや不安を抱くのは自然なこと。
でもその感情の裏には「うまく付き合えればもっと良くなるかも」という希望が、必ずある。
私たちはいま、まさにその揺れの中に立っています。
■ 「黒船」をどう迎えるか
AIを拒むか、受け入れるか。
二択のように語られることもありますが、私はそうは思いません。
AIは、もう港に停泊しています。
完全に締め出すことも、完全に任せることもできない。
だからこそ「共に進む」という選択肢が生まれます。
AIを「脅威ではなく仲間」として見る。
AIを「答えの箱ではなく問いの鏡」として使う。
そのマインドが、これからの時代に求められるのだと思います。
■ 次回予告:第2回「答えを求める思考からの脱却 ― 問いを創る力」
次回は、AI時代における最大のテーマ
「問いを立てる力」について掘り下げます。
AIを使いこなす人と、そうでない人の違いは、実は「問い方」にあるのかもしれません。
「良い問い」が生まれると、AIとの対話が一気に変わる。
次回は、そんな「問いのデザイン」を一緒に考えていきましょう。

